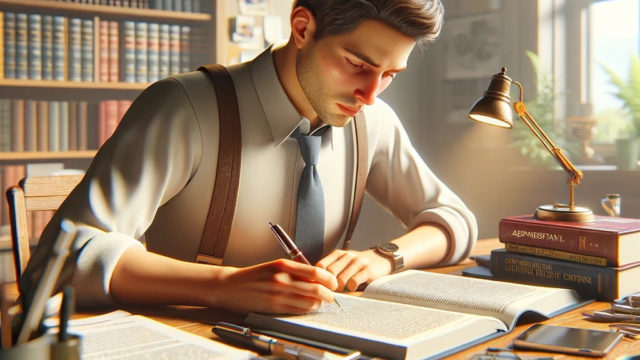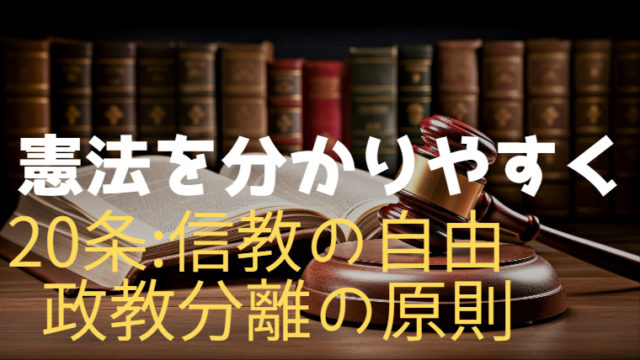憲法22条を分かりやすくまとめると、ポイントは2つの規制と判断基準です。
例えば、争点となった「法律」がどういった目的で制定したのか。という根拠を見極める必要があります。
実は、精神的な自由よりも規制が多いのが、憲法22条です。
行政書士試験の準備にお悩みの方へ。複雑な試験範囲や不安を解消し、自信を持って合格を目指すなら、資格スクエアの行政書士講座がおすすめです。
柔軟な学習スケジュールや24時間対応のサポート体制が整っており、スマホやPCから気軽に学習できます。
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。

憲法22条を分かりやすく!!簡潔に!!
憲法22条は職業選択の自由を認める法律で、「消極目的」「積極目的」という2つの規制の下に成り立っています。
「ある法律」が原因で申請が却下されるなど、その「ある法律」の考え方は憲法22条に反するのではないか。という問われ方をします。
動画でみたい方はこちら
消極目的の場合、厳格な合理性の基準という形で、生命の危険を抑止する考え方を下に、法律や条例を定めます。
薬局距離制限事件のように、県が定めた設置場所の制限は、薬局が隣接することで起こるが影響、健康被害に直結するとは考えにくいため、この距離制限の考え方は無効であると判断されました。
※隣接することによる価格競争が起点で、 不良な医薬品が供給されることは考えにくい。
積極目的の場合、明白の原則という基準となるため、積極目的による規制は、違憲性の判断は緩くなります。
小売市場距離制限事件のように、市場に対する距離制限は、過度な争いによって薄利になることを避ける目的で定めた、小売商業調整特別措置法は、積極目的の考えで定めた法律という判断がされたため、憲法22条1項には反しない。合憲であるとしました。
消極目的の場合は、絶対的に制限するための根拠「厳格な合理性の基準」がない限り、認められない。
積極目的の場合は、明らかな誤り「明白の原則」がない限り、認められない。
- 2つの規制
- 合憲性の判断基準
憲法22条の概要
まずは、概要から見ていきましょう。
憲法22条として、2つ定義されています。
- 何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転および職業選択の自由を有する。
- 何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。
要するに、何処で何しようが自由ですよ。という法律となります。
働かない人達に対して、とやかく言える権利はないと改めて感じました。
まれに海外移住する有名人に対して、いい意見がなかったりする今日この頃の風潮も、憲法22条を知ると不自然に思えてきました。
職業選択の自由と謳われるくらいですから、自由を認めるものだと考えることができるので、言葉だけ見ると非常にありがたい法律ですね。
また、この憲法22条と合わせて謳われるものとして、営業の自由があります。

明確に営業の自由を認めた記載はありませんが、職業選択が自由なら、営業という形も当然認められるという解釈の下に成り立っているようです。
ただし、何でもかんでも自由に職業を選択できるか?というとそうではありませんよね。
仕事に就くために色々な資格や申請、許可が必要なことも多いです。
公共の福祉との関係
憲法22条1項には、公共の福祉に反しない限り、という一文があります。
自由とは言っても、全てOKだとは言っておらず、きちんと規制というルールが大前提となっております。
晩ご飯を食べるという約束しておやつをもらった。
お家のルールを守るという前提があるからこそ、おやつをもらえるという自由が認められます。
とは言え、お家ではルール違反をしても許容されるかもしれませんが、憲法となるとそうもいかないので完全一致とは言えませんが、そんなイメージとなります。
※もしかしたら、1週間おやつ抜きを経験した方もいるかもしれません。

自由にできる中で色々なルールが発生するのが社会であり、そのルールが法律となります。
一方で精神的な自由である、思想の自由と比べると制限が多いのが憲法22条です。
2つの規制
職業選択の自由を認める前に、様々な規制があり、それらの規制、法律などの合憲性については、2つの規制目的から判断されます。
それが、消極目的と積極目的で、二分論という言い方もされます。
いくつかの判例を見ても、この2つ規制による合憲性の判断基準がポイントになっています。。
- 消極目的:厳格な合理性の基準
- 積極目的:明白の原則
消極目的と厳格な合理性の基準
まずは、消極目的です。
消極という言葉からも分かるように、許可や届出、資格といった制限が多くなります。
国民の命や健康を守る目的での制限が発生します。
例えば、飲食店の開業だと、衛生面の許可といった段階を踏む必要があり、非常に手間がかかるようになっています。
しかし、こういった資格や許可が必要でない職業であれば、比較的簡単に開業することができます。
※自宅から郵送で完結します。
そして忘れた頃に確定申告の書類がドンっと登場します。。。
当たり前と言えばそれまでですが、もし消極目的規制がなかったら、誰しもが自由に医者になれる世界が訪れることになり、命や健康を脅かすかもしれません。
このように、命や健康から国民を守る目的の規制が、消極目的規制となります。
この消極目的規制については、立法事実に基づき、以下2つの基準に合憲性が判断されるものと定義されています。
- 規制の必要性、合理性が認められること
- より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないこと
この2つの基準を「厳格な合理性の基準」と呼びます。
要するに、必要であることを証明するためには、強い根拠が必要ということになります。
「立法事実」という言葉があるように、法律による制限やルールの下に商売が成立するということであり、それらの判断基準は、国民の生命や健康を守る目的であるべきであるということになります。
積極目的と明白性の原則
続いては、積極目的です。
こちらは、経済の調和や発展といった目的や過度な価格競争(過当競争)を制限することが目的となります。
生活に直結する電気、ガス、水道といったインフラ、市場などが該当します。
止まらない値上がりが起こる中でも、一部企業だけ激安で「価格崩壊」といったことが発生しないように、国による補助や支援も行いやすい分野となります。
きちんと出勤する会社をイメージすると分かりやすいかもしれません。
積極目的規制は、立法府の広い裁量を認め、規制が著しく不合理であることの明白である場合に限って、
違憲と判断がされるものと考えられています。
簡単にまとめると、積極目的で決められた規制は、明らかにヤバイこと、明白な理由がない限りは違憲という判断はされないということです。
積極目的の判断は経済活動の発展等を目的としているため、それらの法律自体が不合理であることはほぼ有り得ないと判断されます。
参考判例
ここからは、これまでの規制を念頭に置いて、参考判例を見ていきましょう。
厚生労働省のHPに掲載されている、3つの判例を見ていきます。
参考判例1:薬局距離制限事件(消極目的規制)
まずは、消極目的の判例である、薬局距離制限事件です。
どんな内容?
薬局の開設の許可申請を行ったところ、薬事法と広島県が定めた条例によって、設置場所の不適合を理由に許可が下りなかった。
その「場所の基準」は、憲法22条1項に反するのではないか?と処分の取り消しを求め、最終的には距離制限を定める条例は憲法22条1項に反するとの判決がされました。
ナゼ、憲法22条に反するのか。
ここでポイントとなるのが、距離制限を設定した目的と、判断基準です。
改正前の薬事法では、薬局の場所に対する制限は適正な医薬品の供給を目的とする。と定義しているため、距離制限は生命を守る目的とした、消極目的による規制となります。
※距離は県の条例で定めるとし、広島県はおよそ100mとしていた
では、この距離制限によって、健康被害は考えられるか、というと、答えはノー
消極目的の判断基準とは・・・
生命の危険や健康被害を抑止する、厳格な合理性の基準が必要でした。
薬局の隣接→価格競争→質の低下→健康被害?
裁判では、この連想ゲームに絶対的な根拠があるかというと・・・「見当たらない」という判断をしました。
確かに、ゴリゴリの根拠が必要な場面で、このような連想ゲームは、ちょっとツッコミ入りそうだなと思いました。
IT系でも、提案や討論する場面では、絶対的な根拠や裏どりをしないと、納得してもらうことができません。
※勢いで乗り切れることはありません。
こんなことあるかも
家の近所でも近距離に、薬局が大量にある場所があることに違和感を覚えておりましたが、
これは距離制限がないことが理由と考えると少し納得できます。
ちょっと脱線しますが、同じ調剤薬局でも、皮膚が強いなど、専門性があったりします。
※別の調剤薬局を案内された経験ありませんか?
それぞれ専門性を持たせたり、することで差別化を図ることを行うことはありますが、製造元の薬品の質が落ちることは考えにくいですよね。
参考判例2:小売市場距離制限事件(積極目的規制)
2つ目参考判例が、小売市場距離制限事件です。
こちらの判例は、同じ距離制限でも「積極目的の制限」として、判断がされた判例となります。
どんな内容?
小売市場の営業を許可制とする法律として、「小売商業調整特別措置法」があり、同法には、同業による過当競争を避ける目的として、距離制限があります。
この距離制限を無視して市場を建設し、貸付を行ったとしてX社が起訴された。
それに対して、同法の距離制限は憲法22条1項に反すると主張した。
この距離制限は憲法22条1項に反しないとの判決がされ、合憲性が認められました。
小売市場について
少し脱線しますが、まずは小売市場についてです。
小売商業調整特別措置法ではひとつの建物内に複数店舗が存在する形として定義されており、身近なところでいうとショッピングモールなどが該当します。
※何となくは分かってましたが、実際に調べることで理解できました。
ナゼ、憲法22条に反しないのか。
小売商業調整特別措置法は、市場占有率が上昇することで価格競争に発展、利益率が低下する可能性を考慮した法律のため、経済の健全な発展を目的とした、積極目的の法律と判断されました。
積極目的の違憲性を判断する基準はなにか・・・
明らかに不合理であることの理由、明白の原則が基準でした。
要するに、X社が起訴された理由は、正当な理由であって、憲法22条に違反する明確な理由はないという判断がされました。
ただし、判例の中では、個人の経済活動の自由を認める内容の記録があるため、個人の経済活動の自由についての考え方そのものを否定されたわけではありません。
過当競争の影響という観点で、定めた法律ということで、積極目的の法律という位置付けがされ、小売商業調整特別措置法の合憲性が認めた形となりました。
主張を認めるが、明白の原則に値しない所がポイントとなります。
先ほどの薬局距離制限事件の隣接する薬局とは違って、大型ショッピングモールに隣接した、大型ショッピングモールは見たことないですよね。
許可基準としては、700mと定義されています。
参考判例3:医薬品ネット販売権利確認等請求事件(薬事法と憲法22条)
最後の判例が、医薬品ネット販売の権利確認等請求事件です。
こちらの判例は、厚労省が発令した省令に対して、違憲性を求めた裁判となります。
どんな内容?
厚労省が、医薬品の販売を原則対面として、インターネットや郵送による販売を制限する省令を発布しました。
一方で、コンビニでの解熱剤の購入は対面であるため、規制対象にならなかった。
そもそも薬事法に販売方法に関する記述はあるのか。というと、ネット販売を明確に規制する記述はありません。
そのため、薬事法に記載がないことを規制することは、薬事法から逸脱するとして、この省令に対しての違憲性を主張した。
一時は違憲性が認められなかったそうですが、最終的には、憲法22条1項の職業選択の自由に影響を与えるものとして、省令が無効であるという判決が下り、ネット販売は認められました。
もしかしたら、この令和の時代にバファリンをポチれなかった可能性があったことに驚きました。
ここがポイント
ただし、この医薬品ネット販売という行為自体を憲法に反すると認めたわけではありません。
そのため、今後、法律として無効となる可能性が残りました。
今日明日という近い未来というよりは、少し先の未来で禁止される可能性もあるということになります。
成り上がリーガル。
以上です。