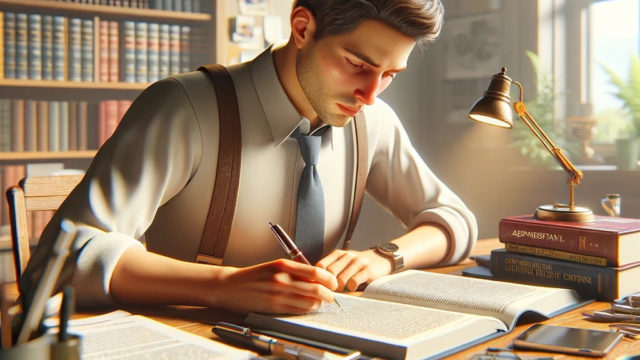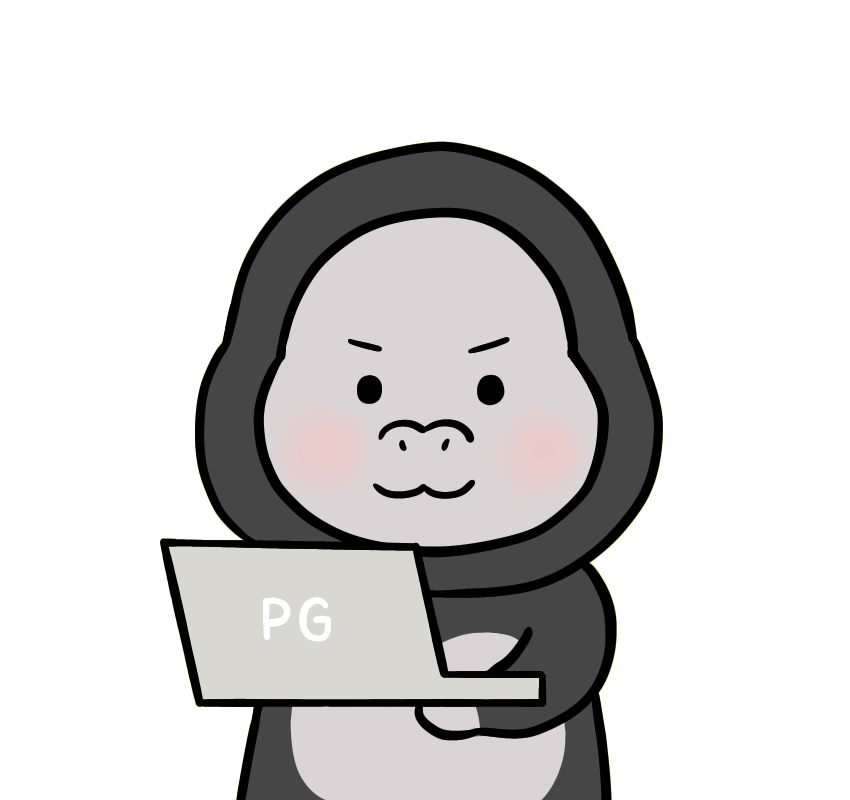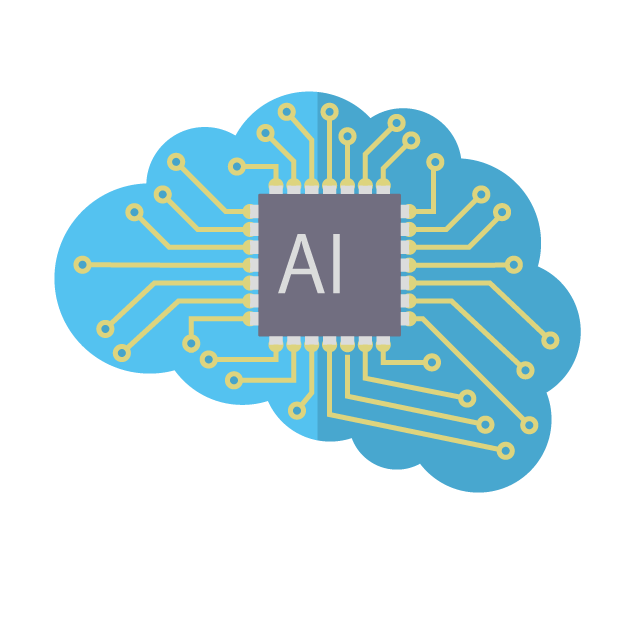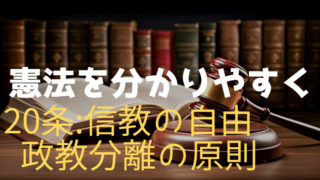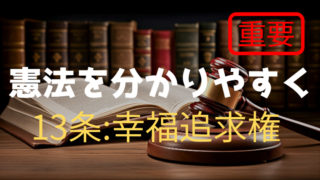日本国憲法の第21条は、言論の自由、出版の自由、その他一切の表現の自由についての基本的な原則を規定しています。
民主主義社会における重要な基本的な価値である表現の自由を保護し、個人やメディアが意見、情報、アイデアを自由に発信できる権利を確立しています。
日本国内における民主主義の根幹をなす原則であり、自由な情報の流通や公共の意見形成に重要な役割を果たしています。
行政書士試験でも最も重要な人権とも言われており、内容も多岐にわたります。
個人やメディアが意見や情報を自由に表現できる権利を与えています。
ただし、公共の秩序や他人の権利を守るためには制約があります。
基本的には、言論や出版の自由を守るが、他者を傷つけるような表現や秩序を乱すようなものについては制限があります。
情報発信することの自由は与えられていますが、近年たびたび問題になるSNSを使用した誹謗中傷など、権利を守るための制約も数多くあります。
最近はとても身近な問題となりましたが、自由は保障されているという点も抑えつつ21条について見ていきましょう。
- 発信の自由と知る権利
- 事前抑制(検閲)
- 表現の自由の限界
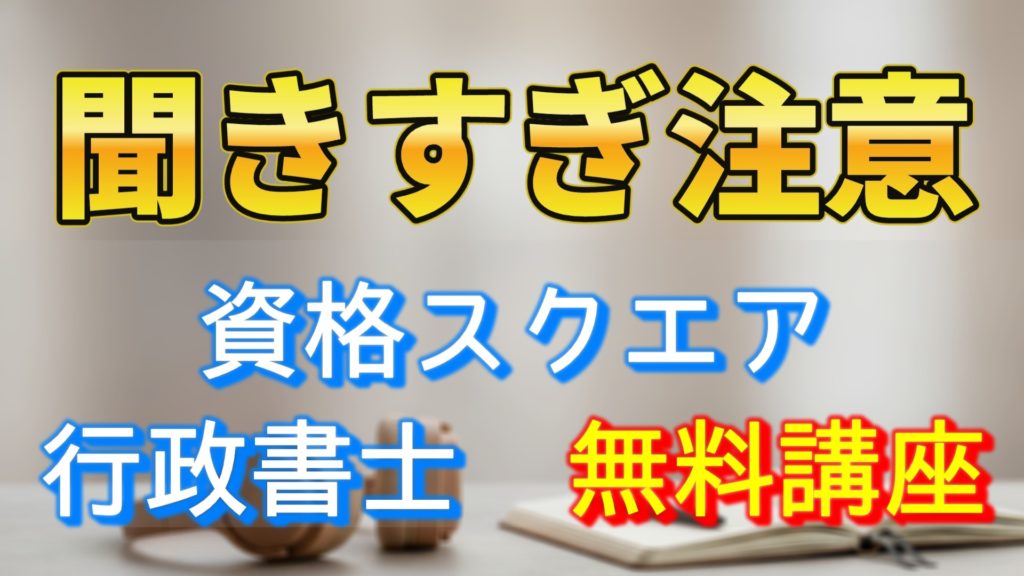
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

憲法21条を分かりやすく!!簡潔に!!
まずは、条文から見てみましょう。
- 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
「言論の自由を守る砦」という表現もされます。(総務省HP)
個人個人が自由に知識や情報、意見と対峙して学びや気づきに変えることは、社会生活を行う上で重要とされており、その行為は欠くことのできないもとと定義されています。
また、それにともなう自由な伝達、交流は必要かつ、当然であるとしています。(法廷メモ訴訟事件)
昔は新聞やテレビが主流でしたが、近年のネット社会でのSNSを使った情報収集や情報発信は社会生活において必要と判断することもできます。
大前提としては、自由が保障されている形となります。
ただし、内心の自由とは違い、絶対的な自由は保障されていませんし、相手を傷つける行為と判断された場合は違憲性を問われることになります。
21条は19条の思想の自由、20条の信教の自由における精神作用を外部に公表することに関しての自由を定義しています。
また、国として表現を制限することはできません。
知る権利として情報を請求することができる権利もあります。
表現の自由を定義する目的
表現の自由を保障する目的として、2つのポイント(価値)があると言われています。
- 自己実現の価値(個人の権利))
- 自己統治の価値(社会的活動))
簡単に言うと、自分らしく生き、理想の自分を形成していくためには「表現」という行為が大きな役割を担っているということです。
自分の意見を他人に言うこと、本音をさらけ出すことは憲法として保障されています。
ただし、ワガママ放題が良いという訳ではありません。
学習や体験、といった経験等をもとに意見することが「自己実現の価値」で、それらを表現する機会を認めることが「自己統治の価値」ということとなります。
自己実現の価値
個人に平等に与えられた権利です。
個人の言論活動や情報発信、知識アップデートは、自己を発展させる価値があるとして、これを保障しています。
数年前までは自分を発信する機会が少なかった印象ですが、近年は自己実現の価値が優遇されている気がしますね。
逆も然り、何も発信しないことも自由とも言えます。
公共の福祉の範囲であれば、自由に学び、発信することができます。
自己統治の価値
個人が言論活動や情報発信を通じて政治に参加する価値を示します。
SNS上で政策に関する意見や討論が行われる場面を目にすることも増えていますが、それらを評価し意見すること、報道することは民主的な価値を生むとされています。
このような意見で国にとって不利な意見があった場合、国家権力として削除を求めることは基本的にはできません。
あくまでも国民の権利として与えられた自由となります。
表現の自由の保障
個人が自分の意見や考えを自由に表現できる権利を保障しています。
これは、政府や他の権力機関からの不当な干渉を防ぎ、政治的な発言や社会的な議論が自由に行われることを意味しています。
出版物を通じた情報や意見の自由な発信を保障しており、新聞、雑誌、書籍、ウェブサイトなど、あらゆるメディアも含まれています。
近年ではXやInstagram、YouTubeなどもこれらに含まれます。
- 言論の自由
- 出版の自由
また、表現の自由があらゆる形態の表現に適用されることも規定しており、音楽、芸術、映画、演劇などさまざまな文化的な表現もこれに含まれます。
制約と制限
表現の自由は無制限ではなく、公共の秩序や善良な風俗を害するもの、他人の名誉を傷つけるもの、国家の安全保障に関わるものなど、一定の制約や制限があります。
このため、法的な枠組みにおいて、表現の自由と他の権利とのバランスを取る必要があります。
あまり見かけることはないかもしれませんが、デモ行進といった集団行動は基本的には21条で保障されている内容となります。
そのため、特別な制約等が設けられている場合には違憲性を問われることもあります。
※地方公共団体の公安条例といった独自のものなど
また、公共施設の利用に際しては条例で許可制をとっているといったケースもあります。
稀に許可が下りないなど、21条の集会の自由を侵害することもあるようです。
公共施設の利用を拒むには混乱を防止できないなどの特別な事情がある場合に限られるとされています。(上尾市福祉会館使用不許可処分事件)
許可制を設けて事前に抑止することは許さないとされていますが、場所等を考慮して許可を設けることは許されるともされています。
集団行動が行われることによる危険性が疑われた場合は許可制は合憲となります。
表現の自由の限界
表現の自由=精神的な自由のため、当然限界もあります。
憲法22条の職業選択の自由よりも厳格な審査が必要とされています。
表現によっては人を追い込むこともできますし、そう考えると案外普通のことかもしれません。
これらを総じて二重の基準と呼びます。
- 経済的な自由(職業選択の自由):合理性の基準
- 精神的な自由(思想、表現の自由):厳格な審査基準
簡単に言うと、法律の憲法的判断が行われる場合、精神的な自由は積極的に裁判所による判断を行い、経済的な自由の場合は、国会の判断が主となります。
名誉毀損に関する事柄は裁判が行われますが、経済的な分野は国会で議論されていますね。
厳格な審査基準(事前抑制,検閲の禁止)
表現を抑制する行為は原則禁止とされており、2項に記載がある検閲の禁止がこれに該当します。(狭義説)
ちなみに1項が事前抑制に当たります。(広義説)
- 行政権が主体となって、
- 思想内容等の表現物を対象とし、
- 表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
- 対象とされる表現物を一般的・網羅的に、
- 発表前に審査した上、
- 不適当と認めるものの発表を禁止すること
検閲は行政権主体で行われてきたことから、実施は行政権に限られているようです。
身近な例で言うと、税関検査は検閲か?ということが問われた判例がありますが、「検閲には当たらない」と解されました。
事前抑制も同じような意味を持ちますが、検閲ほどの絶対的な禁止とはされていません。
※原則禁止としていますが、厳格で明確な要件のもとであれば事前抑制は許されるとしています。(北方ジャーナル事件)
基本的には表現を抑止する行為は禁止されています。
不適切な発言や表現であった場合は当然、削除を求めれる場合もあります。
- 検閲は、絶対的に認められない。(事前抑制等ができる=検閲にはあたらない)
- 事前抑制は厳格かつ明確な要件があれば認められる
まとめ
表現の自由は表現の方法と同じく、多岐にわたるため、行政書士試験でも重要ポイントとされています。
基本的には、情報収集や情報発信は社会生活において必要なこととされています。
それくらい私たちにとって情報や知識は必要なものです。
近年はインターネットの普及、スマホの登場によってより情報を得やすく、発信も容易となりました。
世の風潮としても個人の発信が尊重される時代となりました。
検閲や事前抑制が禁止されているように、法や憲法にも限界があります。
自由の意味を履き違えないようにしたいと改めて思いました。
判例をはじめ、基準も多岐にわたるので、憲法21条はきっちり抑えておきたいポイントです。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
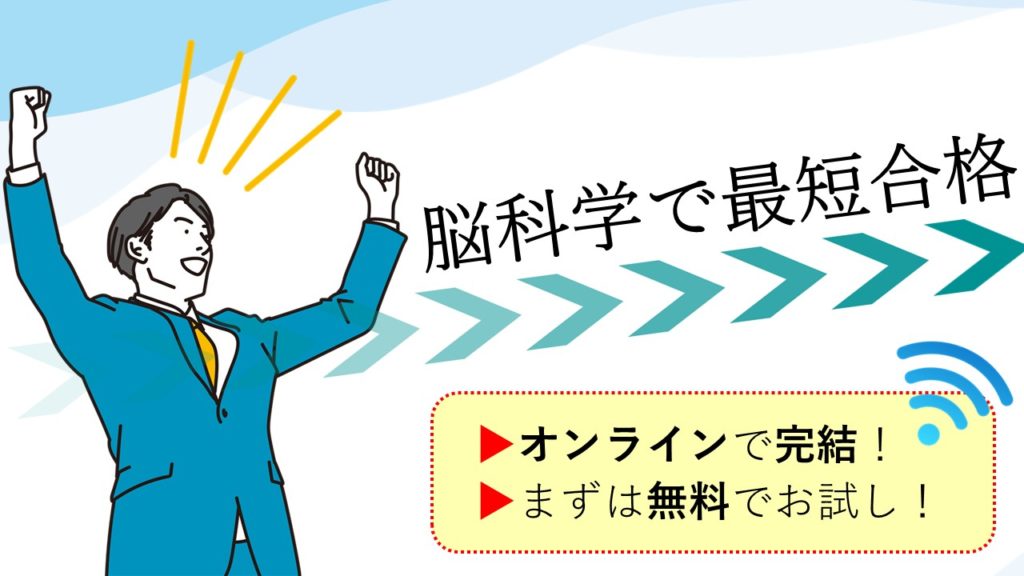
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。