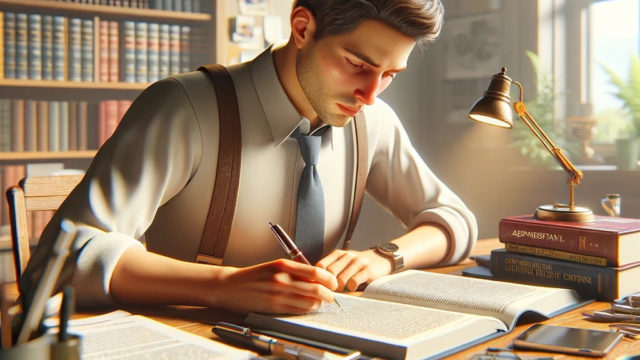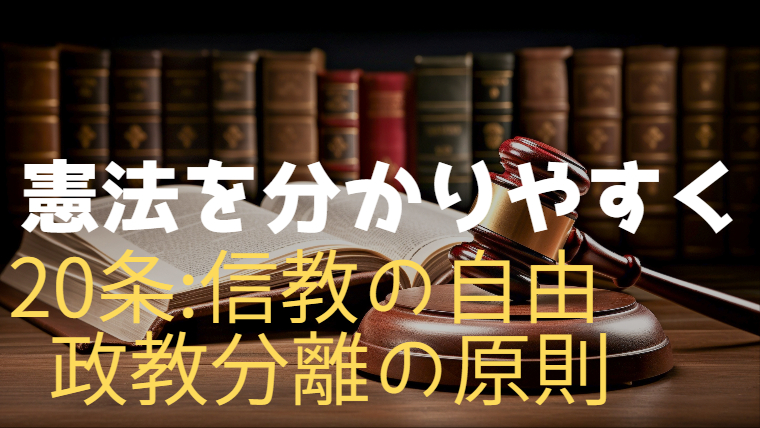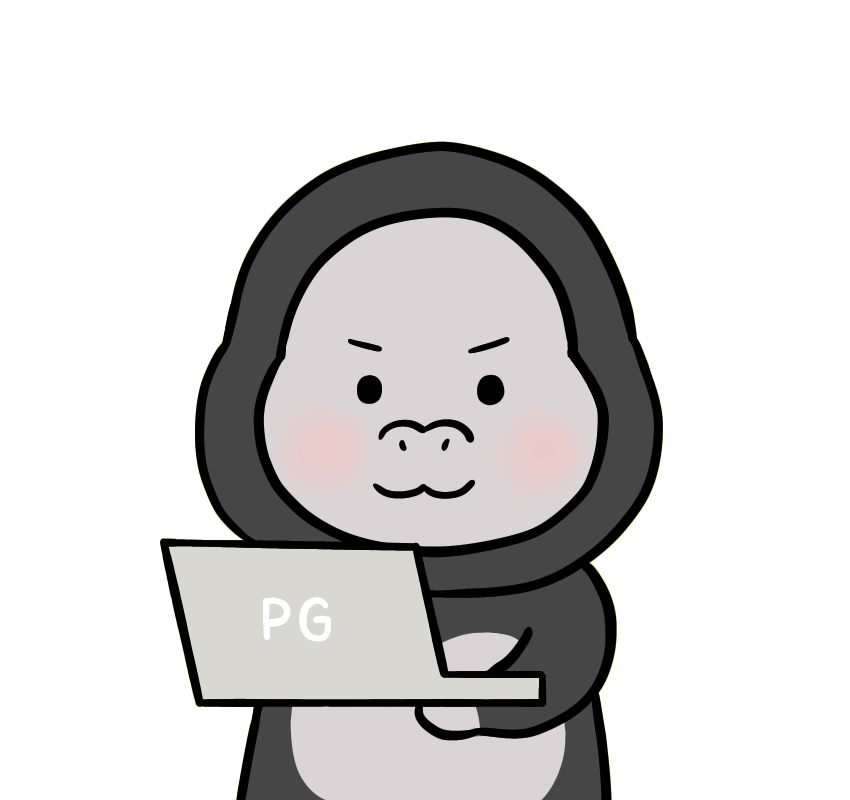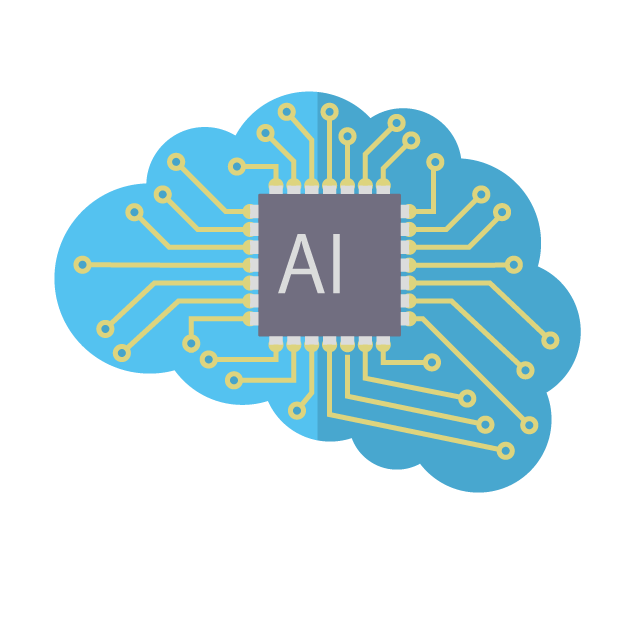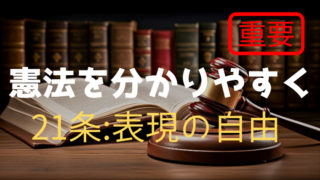憲法20条を分かりやすくまとめると、ポイントは【保障の自由と限界】です。
この憲法20条は内心の自由である19条のように内に秘めた思いではなく、外側での活動に関する自由を保障しています。
そのため、自由の限界ということも20条では重要となってきます。
また、政教分離の原則という政府と宗教という観点も非常に重要となっていきます。
信仰の自由とそれに対する結社の自由は認められていますが、その実施は、公の秩序及び公共の福祉に反しない限りにおいて。であれば認めるというものになります。
- 自由と限界
- 政教分離の原則
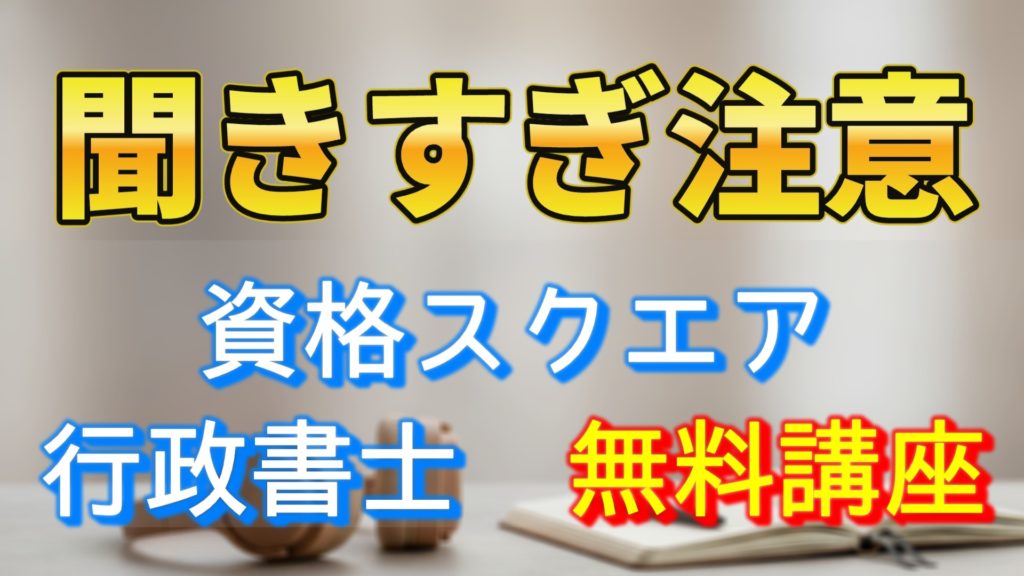
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

憲法20条を分かりやすく!!簡潔に!!
まずは、条文から見てみましょう。
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1の信教の自由は、思想の自由と同様に思うことに留める範囲となるため、絶対的な自由として保障されます。
憲法19条も思うことは自由であることを認める憲法で、もっと言うと自分から公言しない限り、他人から判断することも難しいです。
宗教(教え)もこれと同じで信仰すること(思うだけの範囲)は自由となります。
ただし、2の宗教的行為の自由、3の結社の自由は、文字通りで、思想の範囲にはとどまっていません。
ここには絶対的な自由は保障されていません。
公共の福祉に反しない限りは自由が保障されます
普通に考えると当たり前だとわかりますが、政教分離の原則は目的効果基準が設けられているなど小難しい部分があります。
まずはそれぞれの条文について詳しく見ていきましょう。
信教の自由(絶対的な自由の範囲)
憲法第20条は、個人の宗教的信念や宗教活動に対する干渉を排除し、自由を保障します。
個人は自らの信仰や宗教を選択し、その実践を自由に行うことができます。
あくまでも内心に留める範囲となるため、他人と衝突することは有り得ないこととなります。
そのため、絶対的な自由の範囲であることが分かります。
その自由に信仰することに対して聞き出す行為や、強制する行為は憲法19条で禁止されています。
そして、宗教を信仰しない自由も認められています。
信仰するもしないも自由
宗教的行為の自由(絶対的な自由の範囲外)
この20条では個人だけでなく、宗教団体や教会などの集団も宗教的な活動を行う権利を保障しています。
ただし、この権利を制限するには限界もあります。
基本的には個人や他人と共同で祭壇を設けたり、祈禱を行うような行為は宗教的行為の自由の保障の範囲となります。
※行わない権利も同様に認められています。
ただい、公の秩序や公共の福祉を害する行為や、法の秩序を乱すような活動は保護されません。
オウム真理教解散命令事件のように、宗教団体の解散命令は20条1項に反するのではないか?と問うこともできますが信教の自由の範囲を越えていることがわかります。
このように活動を行うことは、事件へ発展する可能性も少なからずあるため、絶対的な自由は保障されません。
結社の自由(絶対的な自由の範囲外)
宗教的行為の自由と似たようなところがありますが、宗教の宣伝や団体の結成を行う権利も保障されています。
駅前でのビラ配りを見たりや、自宅へ訪問された経験もある人もいるのではないでしょうか。
それは憲法で認められているからです。
※断るのも自由
当然、度が過ぎたり、強制するような行為が行われた場合は、違憲となります。
政教分離の原則(政府の中立性)
基本的には自由が認められていますが、1項にあるように国と宗教は分離することを憲法として定めています。
もし、国が特定の宗教を支持したら?不利益を与える可能性や一部宗教団体が優遇される可能性があり、平等ではなくなる可能性があります。
日本憲法は、宗教と政府の分離を保証しており、国家が特定の宗教を支持することはできません。
宗教的信念や背景に基づく差別や不利益を受けないように保護されています。
※国家の非宗教性、中立性
個人の宗教的自由を保護しながら、公共の安全や秩序を守るためのバランスを考慮しようと意図されていることがわかります。
これによって、個人は自らの宗教や信仰のために、同時に他の人々の権利や社会全体の利益を尊重することも期待できます。
法的性質(法的な性格)
判例において政教分離の原則については、制度的保障としています。
ある制度を保障することで、本質的な部分を侵害せず制度を客観的に保障しています。
政教分離の原則は、個人の権利を保障するのではなく、政教分離の原則の制度を以って信教の自由を保障するものとされています。
※信教の自由を保障するための制度という考え
日本国憲法においては、大学の自治(23条),婚姻制度(24条),私有財産制度(29条),地方自治制度(92条)が制度的保障と規定されています。
政教分離の限界
国と宗教を完全に分離することは難しい部分もあります。
例えば、1の内心の自由の範囲に留めているとしたら、そこを排除することは不可能ですよね。
※自由を制限するという意味でも不合理であると考えることもできます。
そのため、国と宗教の関わりは認めざるを得ないと言われています。
現代の民主主義国家において、絶対主義に近い宗教的な思想は成り立たないという考えのもとから、政教分離の原則が定めらているようです。
政教分離の判断基準(目的効果基準)
国にとして行った行為に違憲性を判断するために、目的効果基準というものが設けられています。
ここまでの行為はOK、これ以上の行為は宗教が得するよね?という基準となります。
政教分離に限界がありつつも、こういった基準を設けることで政教分離の原則を保っています。
※この基準を最初に示した判例が「津地鎮祭事件」です。
- その行為の目的が宗教的意義を持ち、かつ、
- その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
ある宗教が得をする可能性があったり、宗教を援助するような行為があった場合は、目的効果基準としてNGとされます。
政教分離の参考判例
信教の自由である憲法20条としては、政教分離の原則に関する範囲が重要となってきます。
行政書士試験においても政教分離に関する判例を問う問題も多いようで抑えておくべきポイントとなります。
- 津地鎮祭事件
- 愛媛玉串料事件
- 砂川政教分離訴訟
まとめ
憲法20条について、1項については、内心にとどまる範囲となるため、絶対的な自由が保障されています。
しかし、2,3項については宗教的行為も含まれるため、公共の福祉に反しない限りは自由が保障されますが、絶対的な自由ではないことがポイントとなります。
また、国と宗教との関わりということで、「政教分離の原則」というものもあります。
これは、国の中立性を保つことを目的としています。
しかし、個人の思想を制限することには限界がありますし、リソースを割くのも不合理です。
そのため、国の宗教に対する行為の良し悪しを判断するために「目的効果基準」というものがあり、国の行為の合憲性を判断しています。
ちなみに、この政教分離の原則は、制度的保障であると考えられているため、信教の自由を間接的に保障するための制度とされています。
政教分離の原則があることで、信教の自由は認めれていることになります。
単に20条の範囲であれば難しさは感じられませんが、政教分離の原則や目的効果基準が絡んでくると小難しい印象となります。
参考判例でどういった判断がされたかや、目的効果基準を抑えておくとよいでしょう。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
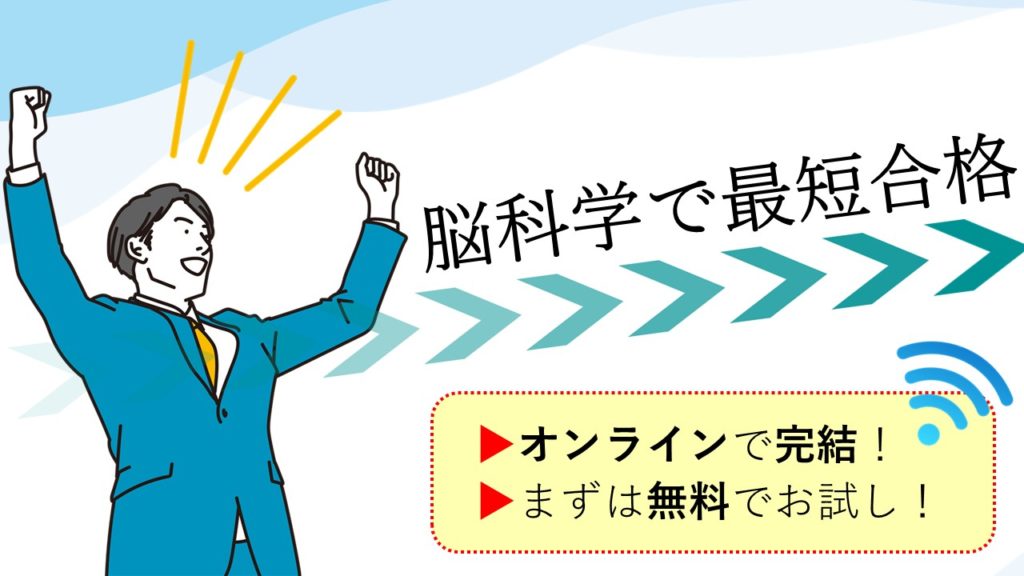
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。