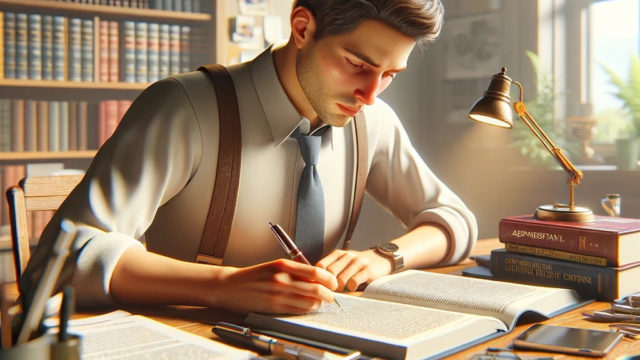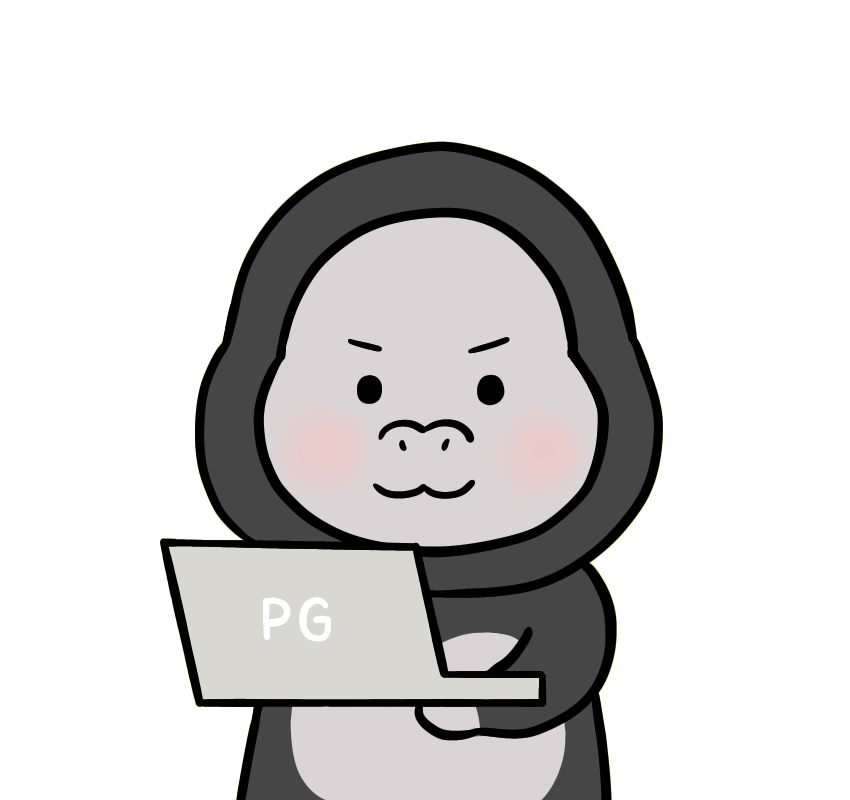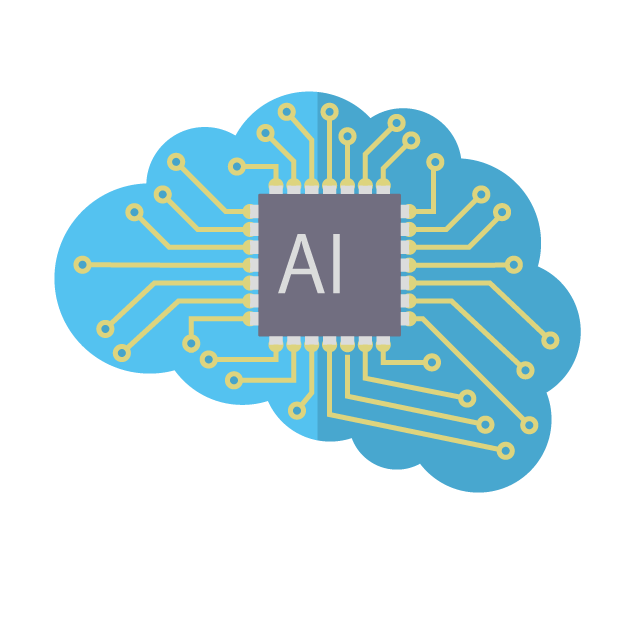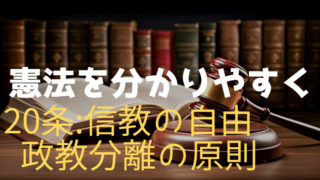憲法19条を分かりやすくまとめるポイントは、3つあります。
それが、内心の自由と沈黙の自由、不当の禁止です。
何か思っても自由で、その思想を外部から判断することも、強制することもできません。
例えば、起立斉唱を促す行為を憲法19条に違反すると判断することはできません。(君が代起立斉唱の職務命令(最判平23.5.30))
人々が自分の信念に基づいて考え、信仰し、その表明をする自由を守ることを意図しています。
また、他者が強制的にこれらの自由を制限されない権利も保障しています。
憲法第19条は、日本国憲法における基本的な人権の一つであり、個人の尊重と自由な意見表明を重視しています。
自由に考えることができるし、どんな思想を持っていようが自由という法律ということだと解釈しました。
さらに、その思想を聞き出したり、禁止したりすることを強制できないという意味もありそうですね。
もっと言うと、心の中でどんな思想を持っていようが、公共の福祉に反しない限りは国家や法律から不当な扱いを受けることはないということになりますね。

- 何を思っても自由
- 思想は強制されない
- 思想によって不当な扱いは受けない
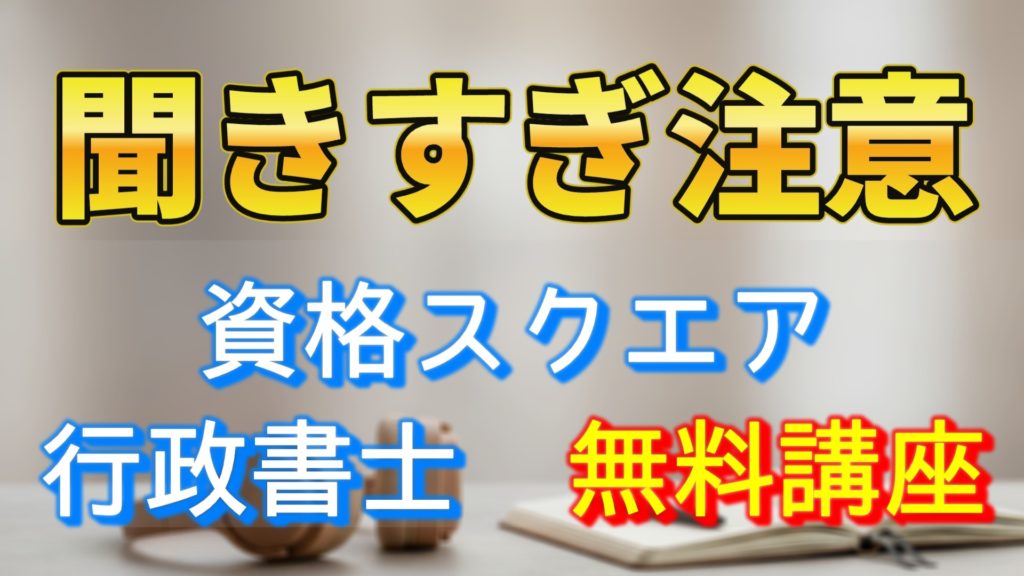
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

憲法19条を分かりやすく!!簡潔に!!
すべて国民は、思想、良心及び信教の自由を有、強制も受けない。信教の自由は、何者に対してもこれを保障する。
学生時代に社会科の授業で勉強したようなキリスト教徒に対する踏み絵や、宗教による儀式への参加を強制すること、信仰を強制するようなことは、日本国憲法19条では違憲となる可能性があります。
憲法19条の思想および良心の自由とは、心の中で思う限りの範囲なので、発言や行動によっては、違憲となる場合があります。
ただし、思うまでに留めるのであれば、何を思っても自由が保障されています。

また、思想の自由に対しては自分の内側に留める範囲であれば、国家権力であろうとそれを禁止することはできないため、「絶対的な自由」とも言われています。
- 内心は何を思っても自由
- 思想を禁止することは国家権力でもできない
国民がどのような思想を抱いているかを聞き出すことは憲法19条によって禁止されています。
つまり、国家権力で何を考えるか聞き出してきたとしても、答える権利はありませんし、答える必要もありません。
そして、思想を聞き出す行為自体が違憲となります。
日本国憲法なので、公共の福祉に反しない限りという制約はもちろんあります。

内心の自由①:思想の自由
思想および良心の自由は、個人が自己の信念や意見を自由に形成し、表現する権利を保障しています。
この観点では、個人は自己の考えや信念に基づいて行動する自由を表していますが、前述したように公共の福祉に反しない限りという制限が付きます。
思想を押し付けたり、思想を持って行動→危害を加えるなどといった場合は、思想の自由は認められません。
※当然のことですね。
また、政府や他人は、特定の思想や信念を押しつけたり、それを制限することはできません。
個人は自分の良心に従って行動し、考える権利を表します。
似たような憲法として、20条の信教の自由、21条の表現の自由もこの19条と深い関わりがあります。
内心の自由②:信教,信仰の自由
内心の自由では、何を思っても自由ということでしたが、信教の自由として個人が自分の宗教を選択し、信仰し、実践する権利も保障されています。
※詳しくは憲法20条
自由に宗教を信仰することもできますし、宗教といったものを信仰しないことも自由となります。
そして、政府や他人は、個人の信仰や宗教上の行動を制限することは当然、許されません。(沈黙の自由)
ちなみに、政府は特定の宗教を支持することは「基本的」にはできないものとしています。
(政教分離原則)
関わりを完全に排除しきれないのが実際です。
沈黙の自由:強制の禁止
前述したように、心に思うことはもちろん、自由を制限することも許されません。
いかなる形の強制も受けない権利とも言えます。
そのため、個人の信念や信条を変えさせようと強制する行為を禁止するという圧力を防ぐ意味もあります。
例えば、どういった思想を抱いているのか。といったことを強制的に公言させることは国家権力であっても許されないとしています。
不当な扱いの禁止:信教の自由の保障
信教の自由の保障は、誰に対しても平等に信教の自由を守る権利も保障されています。
政府や他者が特定の宗教を支持したり、排除することは禁止されていますが、その支持することで不当な扱いをすることも禁止されています。
例えば、特定の宗教を信仰していることを理由に税金を高くする。といった行為はできません。
考えだしたらキリがなさそうですが、思想を理由に何かを排除することは憲法19条に違反となります。
日常生活でも特定の考え方、思想を持っている人を毛嫌いする場面があったりしますが、人様に迷惑をかけていない以上は毛嫌いする行為の方が問題とも考えることができます。
参考判例
憲法19条の思想、良心の自由が争点となった判例について見ていきます。
最大判昭31.7.4:謝罪広告事件
こちらの判例は、謝罪広告を強制した行為に対して憲法19条の違憲性が争点となりました。
どんな内容?
選挙活動中であった2人(A,B)の候補のうち、Aが業者から金銭を受け取った事実をBが新聞等を通じて公表。
それに対して、Aが虚偽の事実であり、名誉毀損として謝罪文の掲載を求めた。
Bは謝罪広告を強制することは思想の自由に反するのではないかと主張した。
結論としては、「違反しない」とされました。
ナゼ、憲法19条に反しないのか。
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」であれば、思想の自由を侵害しない
単純にごめんなさい。申し訳ございませんでした。といった事実を述べ、謝る程度であれば問題となりません。
謝罪という部分の色合いが濃くなると、違憲性が伺えますが、事実を告白するだけのレベルであれば、謝罪<告白となるため、合憲となります。
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる
名誉毀損と判決された場合は、謝罪広告の掲載が命じられます。
※公共の福祉に反したと判断される
最判平23.5.30:「君が代」起立斉唱拒否訴訟
こちらの判例は、国歌斉唱を起立斉唱かつ国旗に向かって斉唱することを命じた校長の命令に対して、憲法19条に反するのではないか。という観点で争われました。
結論としては、「違反しない」とされました。
ナゼ、憲法19条に反しないのか。
まず、国旗に向かった国歌斉唱と聞いて、面倒くさいという思いはあっても、違和感を覚える人は少ないですよね?
というくらい当たり前の慣習であって、出席している保護者含めてその光景を目にした時に、特定の思想を押し付けられている。とは思いません。
逆に言うと、この職務命令に対して何を思うのも自由ですし、思想を強制された訳でもないため、違反するという判断にはならないとされました。
実際に学生時代は、面倒くさいとは思ってはいましたが、何となく従ってましたね。
※違反しないという結果が考え深いなと思いました。
もしかしたら、この職務命令に従わないことが原因で不当な扱いを受けたという事実が証拠として上がっていたら、違反するといった判断がされていたかもしれません。
憲法19条は思想に関連しないものは保障の範囲とならない
まとめ
行動といった形で危害が加わるようなことがあれば当然、違憲であることはわかりますが、思想といった私生活で目にすることができない内面の部分に関わる法律なので、難しい印象ですね。
ただし、近年は本サイトのように思想を自由に表現できる場面が多くなっています。
便利さは増したとは言え、目に見えない相手への誹謗中傷といったことも目にするようになりました。
精神の自由と呼ばれる憲法がいくつかある中でも憲法19条については、思想(内心)の自由を定義しています。
思うことは自由ですが、自由を履き違えないようにしたいなと改めて思いました。
単純な謝罪広告といった形だとしても真相告白の意向が強ければ、19条に違反しない。ここをしっかり抑えておきましょう。
成り上がリーガル。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
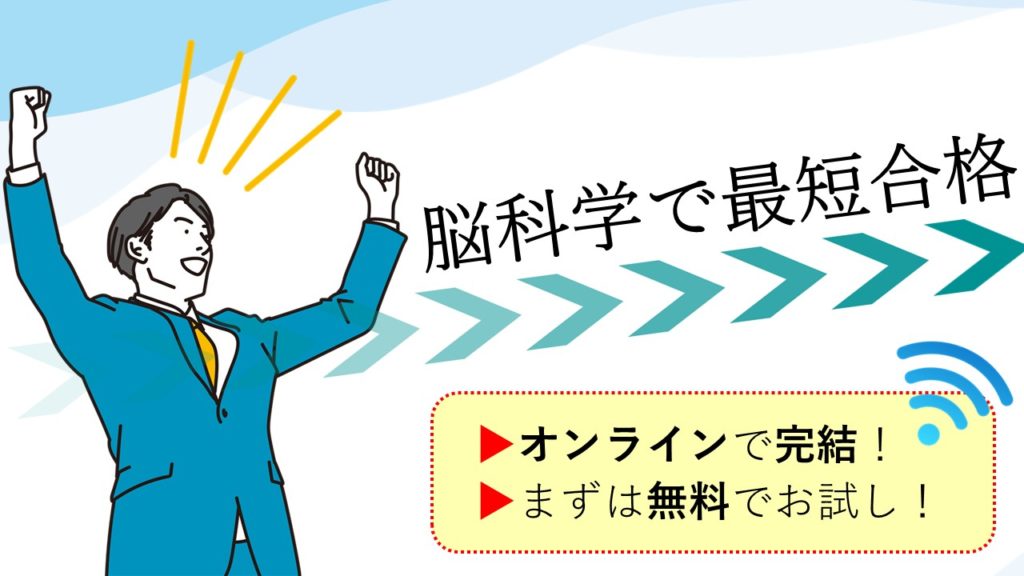
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。