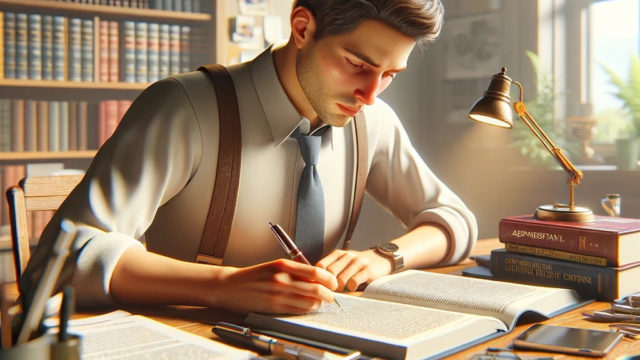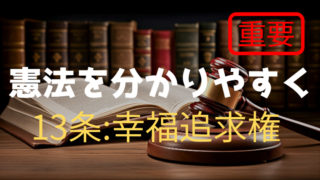行政手続法とは、行政活動における公正性と透明性を確保し、国民の権利と利益を保護する法律です。
行政手続きにおける事前チェックの役割を果たす法律でもあるため、行政法のトップバッターとも言える存在です。
行政手続法全体としてのポイントをまとめると下記となります。
- 処分、行政指導、届出、命令等の制定の手続きに関する規定が含まれる。
- 公正な行政運営と透明性の向上を目指すためのもの。
- 国民の権利利益を保護し、行政の恣意的な行為を防止する。
- 行政作用の適切さを監視する役目を担う。
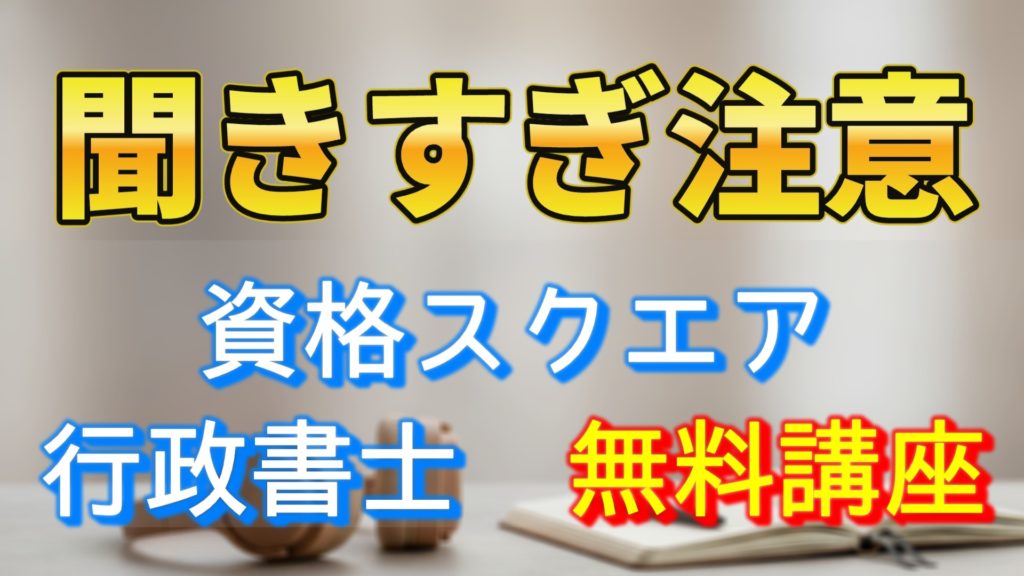
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

行政手続法とは?「対象」と「目的」
まずは、行政手続法の対象と目的を定義している、第1章の(目的等)の条文を見ていきましょう。
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
行政手続法とは、国民が行政によって受ける不利益を予め抑止するための法律(一般法)とされています。
行政が行う行為によって、国民が不利益を受けた場合は、行政不服審査法、行政事件訴訟法といった行政救済を目的として法律によって争うことができます。
しかし、事後的な争いでは対応しきれない場面もあります。
※迷っている、揉めているうちに、別の人に取られてしまったという感じ
そこで、事前に不利益を受けないようにすべく、行政作用を行うための規定を示しているのがこの行政手続法となります。

また、行政手続法は、公正な行政運営と透明性の向上を目指し、国民の権利と利益を保護することを目的としていることが条文から読み取ることができます。
行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等の制定に関する規定を定めています。
条文によって、これらに限られているため、行政計画といったものには行政手続法の規定は及びません。
- 処分
- 行政指導
- 届出
- 命令等の制定
ただし、例外もあり、どうしても行政手続法の適用を除外すべき行為もあります。
適用除外と言い、行政手続法の対象から除外されます。
※早慶戦の日は休講(お休み)、会社の創立記念日は半日になるなどの特別扱いのイメージ。
行政手続法の目的は、上記4つの手続きに関して共通的に規定を設けることによって、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図っています。
これらを定めることで国民の権利利益の保護を目的としていることがわかります。
また、2項で明記している内容から、他の法律に定めがある場合は優先されているという点は押さえておきたいポイントです。
行政手続法のポイント
処分
処分とは、行政機関が行う決定や措置のことで、申請に対するものと不利益に対するものの2種類に分類されます。
法的義務と努力義務の棲み分けといった形を理解しておく必要があります。
例えば、基準を定めることが努力義務であっても定めた場合には、公にする必要がある。という、法的義務が課せられます。

行政指導
行政指導とは、行政機関がその任務、所掌事務の範囲内において、行う指導、勧告、助言その他の行為であり、処分に該当しないものと定義されています。
例えば、生活保護申請者に家族からの援助をお願いするといった、行為のことを言います。
届出
届出とは、行政庁に対して事実を通知するという一方的な行為を示すため、応答を求める申請とは異なります。
※メール送って終わりのイメージです。
個別の法令での届出とは異なり、行政手続法的には申請もしくは届出のどちらかに該当するかの判断が必要となります。
命令等の制定
命令等制定機関が、法令の趣旨に適合するようにすることを示す一般原則です。
命令等を定めた後のアフターサービスも条文として定義されており、社会情勢による変化や実施状況といった状況から観点から検討を行い、適正を確保するように努めることが条文として定義されています。
また、2005年の法改正によって法定された、意見公募手続もポイントとなっていきます。
適用除外
ここまでの4つ(処分、行政指導、届出、命令等の制定)であっても行政手続法上はなじまないものもあり、適用除外と呼ばれています。
簡単にまとめると、下記になります。
- 行政手続法が定める手続を執っても無駄なもの
- 行政手続法よりも慎重な処理が必要なもの
- 処分の性質上、なじまないもの
この他にも法律、条例によって適用有無が異なる部分があるなどのポイントを押さえておく必要があります。
まとめ
行政手続法は、国民の権利と利益を保護し、行政運営の公正性と透明性を確保するための重要な法律です。
処分、行政指導、届出、命令などの手続きに関する規定が定められています。
それぞれの規定の中で細かい分類もあるため、そこも大切なポイントとなっていきます。
また、適用除外といった、性質上なじまないものがあることも重要となってきます。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
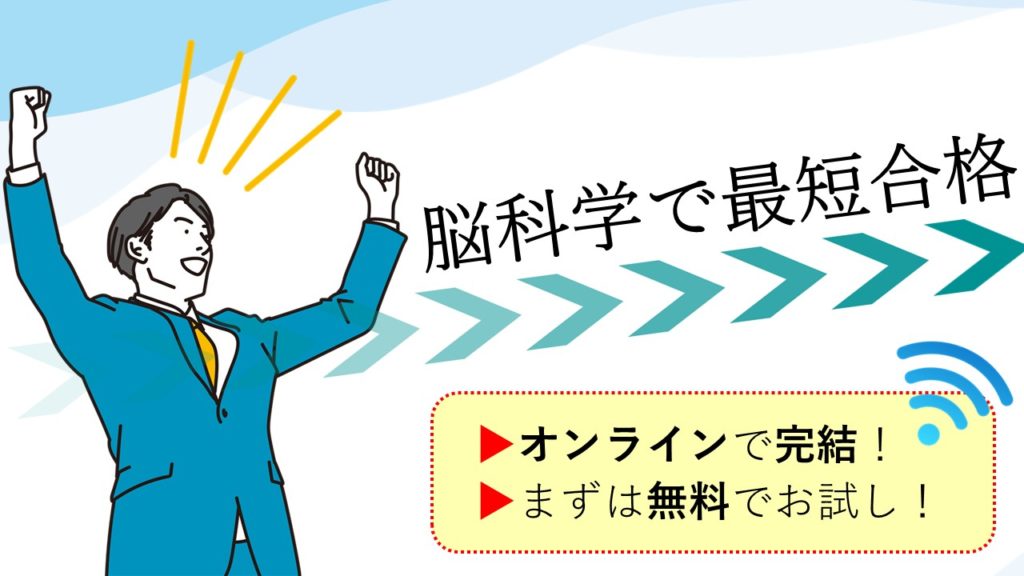
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。