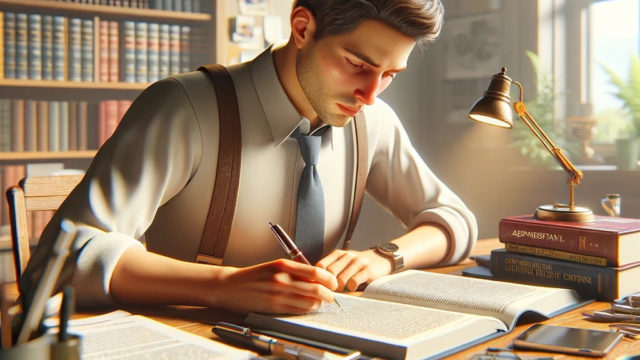国家賠償法と損失補償の違いは、その行政作用がどういったものかがポイントとなります。
行政の行った行為等によって損害を被ったとき、補償を受ける権利があるかもしれません。
その救済策となるのが「国家賠償」と「損失補償」です。
これらの違いを表でまとめながら解説していきます。
簡単に言うと、国家賠償は、行政が「違法な」行為をして損害を与えた場合に請求できる賠償で、警察官の不当逮捕、役所の個人情報漏洩などが挙げられます。
損失補償は行政が「適法な」行為をした結果、特別な損失を被った場合に請求できる補償で、道路拡張工事による立ち退き、公共事業による土地収用が挙げられます。
「違法(賠償)」「適法(補償)」という差が一番のポイントとなります。
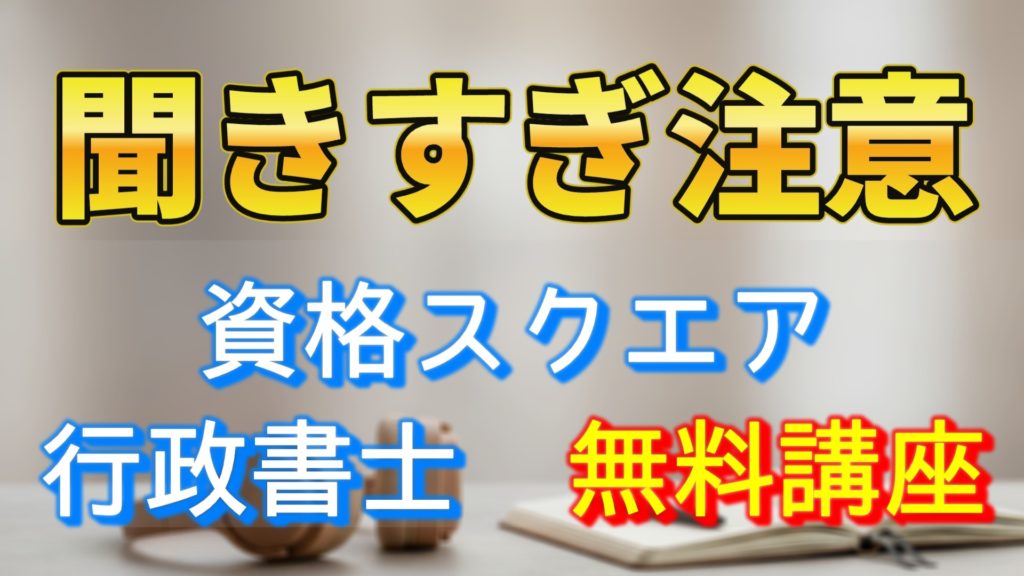
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

国家賠償法と損失補償の違いを『表』で体系的に理解!!
国家賠償と損失補償は、どちらも行政の行為によって損害を被った場合に、その損害を補償するための制度です。
しかし、その内容や請求できる要件には、大きな違いがあります。
| 項目 | 国家賠償 | 損失補償 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 国家賠償法(憲法17条) | 個別の法律(例:土地収用法、道路法など)(憲法29条3項) |
| 行為の性質 | 違法な公権力の行使 | 適法な公権力の行使 |
| 保護する利益 | 個人の権利・利益 | 財産権 |
| 賠償の範囲 | 原則として全損害 | 法律で定められた範囲の損害 |
| 請求先 | 加害行為を行った国または公共団体 | 個別の法律で定められた機関(事業主体など) |
| 過失の有無 | 過失が必要(1条責任)または不要(2条責任) | 不要 |
| 時効 | 損害発生時から5年、賠償義務者・損害を知った時から3年 | 個別の法律で定められた期間 |
| 例 | 警察官の不法逮捕、道路の欠陥による事故 | 道路拡張工事による立ち退き、公共事業による土地収用 |
国家賠償:違法な行為に対する賠償
国家賠償は、国や地方公共団体が違法な行為によってあなたに損害を与えた場合に、その損害を賠償してもらうための制度です。
例えば、警察官に不当に逮捕された、壊れていた道路のせいで転んでケガをしたなどの、違法性が認められるケースです。
損失補償:適法な行為に対する補償
一方、損失補償は、国や地方公共団体が適法な行為を行った結果、特別な損失が生じた場合に、その損失を補償してもらうための制度です。
要するに問題がない状態にも関わらず、私たち国民に重大な損害があった場合に適用されるものになります。
例えば、道路拡張工事で立ち退きを迫られた、公共事業のために土地が収用されたといったケースが当てはまります。
| 制度 | 対象となる行為 | 請求の根拠 |
|---|---|---|
| 国家賠償 | 国や地方公共団体の違法な行為 | 国家賠償法(憲法17条) |
| 損失補償 | 国や地方公共団体の適法な行為 | 個別の法律(例:土地収用法、道路法など)(憲法29条3項) |
損失補償をくわしく
損失補償は、適法な公権力の行使によって生じた損失を補償する制度ですが、その内容は法律によって異なります。
損失補償の根拠となる法律は、個別の法律で定められています。
例えば、下記のような法律が挙げられます。
- 土地収用法:公共事業のために土地を収用する場合の補償を規定
- 都市計画法:都市計画事業のために土地の区画整理や建築制限を行う場合の補償を規定
- 道路法:道路整備のために土地を収用したり、建築制限を行う場合の補償を規定
どんな損失が補償されるか。
損失補償の対象となる損失は、財産上の損失に限られます。
例えば、土地や建物の価値の減少、営業利益の減少といったケースです。
損失補償の対象となる損失が財産上の損失に限られる根拠は、主に以下の2つが挙げられます。
1.憲法29条3項の規定
損失補償の根拠となる憲法29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しています。
この条文は、私有財産権の保護を目的としており、公共の利益のために私有財産を収用する場合には、正当な補償が必要であることを定めています。
ここでいう「私有財産」は、土地や建物などの有形財産だけでなく、特許権や著作権などの無形財産も含みますが、いずれも財産的価値を持つものです。
したがって、憲法29条3項の文言上、損失補償の対象となるのは、財産上の損失に限られると解釈されます。
補償の支払時期については、憲法で規定されているわけではありませんので、注意が必要です。
土地の引き渡しと同時に行われなかったとしても違法性はありません。
支払時期まで憲法で保障しているわけではない
2. 判例の解釈
判例においても、損失補償の対象は財産上の損失に限られるという解釈が一般的です。
最高裁判所は、損失補償の対象となる損失について、「社会的制約として一般的に受忍すべき限度を超え、かつ、それが平等原則に反するような個別的負担である特別の犠牲」(最判平成17年11月1日)と定義しています。
この定義からも、損失補償の対象となるのは、財産権に対する特別な侵害であり、精神的苦痛などの非財産的損害は含まれないと解釈されています。
まとめ
国家賠償と損失補償は、どちらも行政の行為によって損害を被った際に補償を求める制度ですが、その内容は大きく異なります。
国家賠償は、国や地方公共団体の違法な行為、例えば、警察官の不当逮捕や個人情報漏洩などによって損害を受けた場合に請求できます。
これは、個人の権利や利益を守るための制度であり、国家賠償法に基づき、原則として全損害の賠償が認められます。
一方、損失補償は、国や地方公共団体の適法な行為、例えば、道路拡張工事や公共事業による土地収用などによって特別な損失を被った場合に請求できます。
これは、憲法29条3項に基づき、個別の法律で定められた範囲の損害が補償されます。
例えば、土地収用法では、土地の収用によって生じた損失に対して補償が規定されています。
国家賠償と損失補償は、請求先も異なります。
国家賠償は加害行為を行った国や地方公共団体に請求しますが、損失補償は個別の法律で定められた機関(事業主体など)に請求します。
どちらの制度を利用するべきかは、損害の原因となった行政の行為が違法か適法かによって判断されます。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
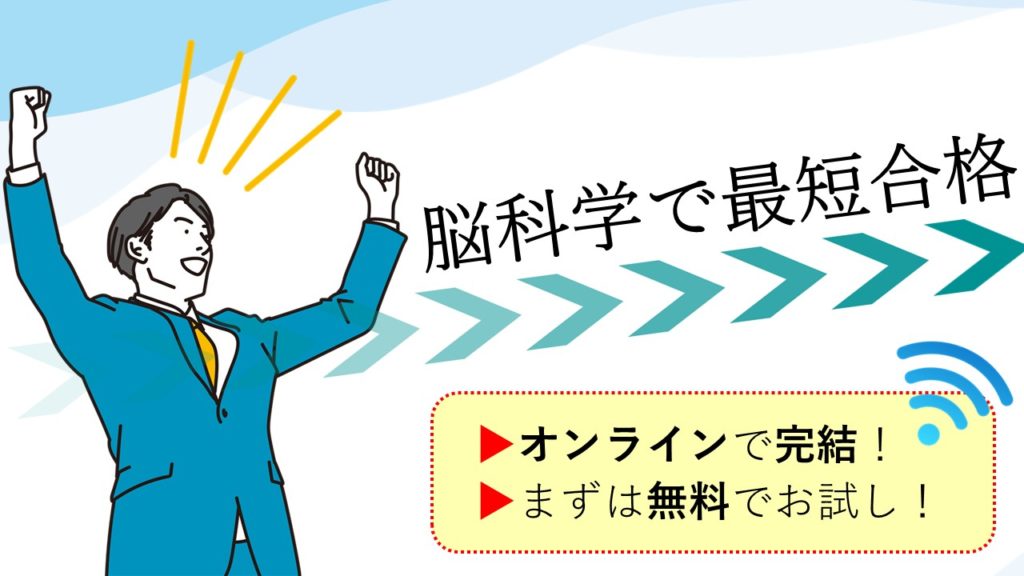
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。