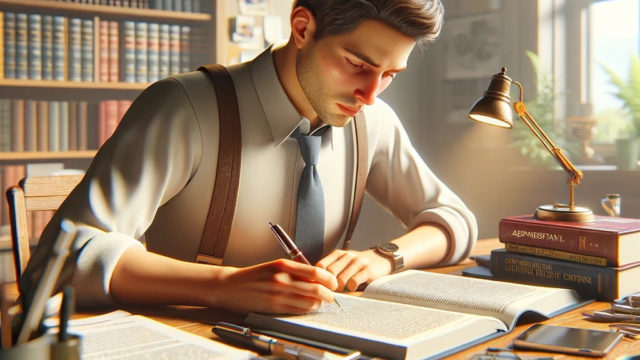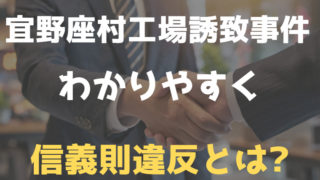行政法の一般原則をわかりやすくまとめると、行政の行動を律する基本的なルールであり、私たちの権利と利益を守るために必要不可欠なものです。
行政法の一般原則は、行政の権限行使を制限し、国民の権利利益を保護するための重要なルールです。
法律による行政の原理と一般原則を理解し、具体的な事例や判例を通して、これらの原則がどのように適用されるのかを見ていきましょう。
まず、行政法の一般原則は法律による行政の原理と一般原則の2つに分類されます。
- 法律による行政の原理
- 法規創造力の原則:法律は国会のみが制定できる
- 法律優位の原則:行政は法律に違反してはならない
- 法律留保の原則:国民の権利を制限するには法律の根拠が必要
- 一般原則
- 信義誠実の原則:行政は誠実かつ公正に行動しなければならない
- 濫用禁止の原則:行政は与えられた権限を目的外のことに使ってはならない
- 比例原則:行政は目的達成に必要な範囲内で最も制限の少ない手段を選ばなければならない
- 平等原則:行政は合理的理由なく差別してはならない
- 説明責任の原則:行政は自らの行為の理由を国民に説明する義務を負う
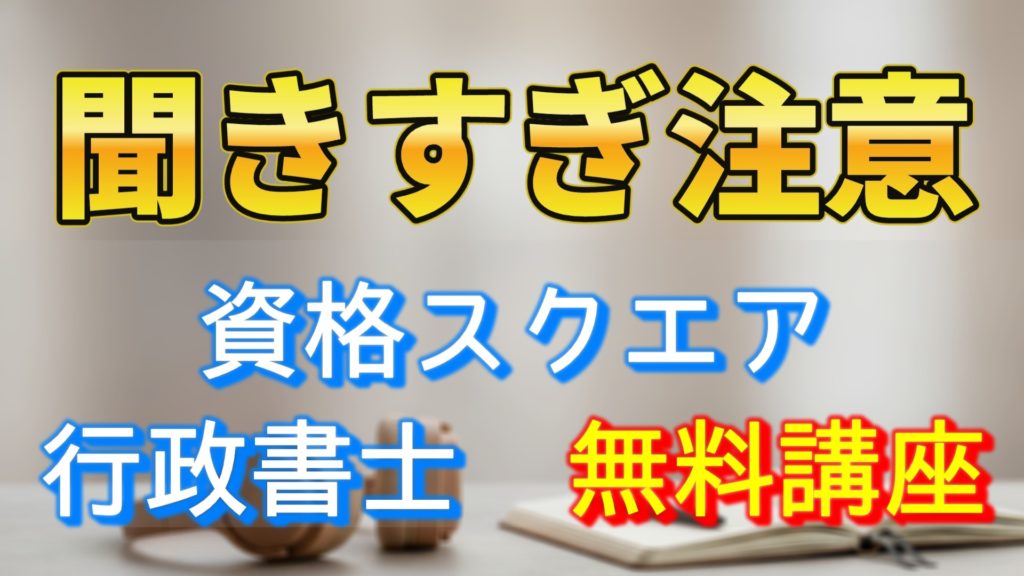
※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。

行政法の一般原則は、行政の「当たり前」
行政法の一般原則は、行政が活動する上での基本的なルール、いわば「当たり前」のことを定めたものです。
例えば、私たちは日常生活で、赤信号で止まる、人を差別しないといったことは、至極当然とも言えます。
行政も、私たちと同じように、法律や社会のルールに従って行動しなければなりません。
行政法の一般原則は、行政にとっての「当たり前」を明確にすることで、私たちの権利や利益を守り、公正な社会を実現するための基盤となっているのです。
行政法の一般原則は、大きく2つに分けることができます。
- 法律による行政の原理
- 一般原則
それぞれ詳しく見ていきましょう。
| 法律による行政の原理 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 法規創造力の原則 | 法律は、国会のみが制定できる | ある市が「ペットの飼育は禁止」というルールを勝手に作って、市民に強制することはできない |
| 法律優位の原則 | 行政は、法律に違反してはならない | 法律で「建築許可の申請から30日以内に審査結果を通知しなければならない」と定められているのに、行政が60日経っても通知しない場合、その行為は違法となり、取り消される可能性がある |
| 法律留保の原則 | 国民の権利を制限したり、新しい義務を課したりするような行政行為は、法律の根拠が必要 | 行政が土地を強制的に収用するには、法律の規定が必要 |
法律による行政の原理
法律による行政の原理とは、行政の活動が法律に拘束されることを指します。
行政活動は私たちの生活に非常に大きい影響を及ぼすことはわかると思います。
そんな行政活動が気分で適用にされては困ります。
そこで、国家の唯一で立法の最高機関である国会が定めた法律には従わなければならない。ということを行政法の一般原則として、法律による行政の原理と言われます。
法律による行政の原理には3つの原則があります。
法規創造力の原則
法規創造力の原則とは、「法律は、国会のみが制定(創造)できる」という原則です。
行政は、法律の範囲内で活動しなければならず、勝手に新しいルールを作ることはできません。
例えば、ある市が「ペットの飼育は禁止」というルールを勝手に作って、市民に強制することはできません。
このようなルールを制定するには、国会の議決を経て法律にする必要があります。
法律を創造できるという風には考えず、人の権利義務を決めるような法規の創造は法律によってのみできるという原則になります。
法律優位の原則
法律優位の原則とは、「行政の権限(行政活動)だとしても法律が優先される」という原則です。
当たり前ですが、行政活動は、常に法律に適合していなければなりません。
もし、行政が法律に違反する行為を行った場合、その行為は無効とされます。
例えば、法律で「建築許可の申請から30日以内に審査結果を通知しなければならない」と定められているのに、行政が60日経っても通知しない場合、その行為は違法(不作為)となっていきます。
このように均衡が保たれていることで規律が成り立っているともいえます。
法律留保の原則
法律留保の原則とは、「国民の権利を制限したり、新しい義務を課したりする場合は法律の根拠が必要である」という原則です。
根拠となる法律が規定されている必要があります。
ただし、全てが根拠が必要というわけではないことは注意が必要です。
国民の権利を制限とあるように、国民の権利義務に関する行政活動を行う場合は、法的根拠が必要となります。
例えば、行政が、ある人の土地を強制的に収用する場合、法律に「公共の利益のために土地を収用できる」という規定がない限り、収用することはできません。
この原則は、行政の権限を制限し、国民の権利を守るために、非常に重要な役割を果たしていることがわかります。
一般原則
一般原則とは、法律に明文の規定がない場合でも、行政が遵守すべき基本的なルールのことを表します。
行政法におけるモラルともいえます。
| 一般原則 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 信義誠実の原則 | 行政は、誠実かつ公正に行動しなければならない | 補助金を交付することを約束したのに、正当な理由なく交付しないことはできない |
| 濫用禁止の原則 | 行政は、法律の付与した権限を、その目的の範囲を超えて行使してはならない | 警察官が、職務質問の権限を乱用して、無関係な人々を長時間にわたって拘束することは許されない |
| 比例原則 | 行政は、目的達成に必要な範囲内で、最も制限の少ない手段を選択しなければならない | 騒音問題を解決するために、工場の操業を完全に停止させるのではなく、防音壁を設置するなどの手段を選ぶ |
| 平等原則 | 行政は、合理的理由なく、人々を差別的に扱ってはならない | 同じ条件の2人に対して、一方には許可を与え、もう一方には許可を与えないことはできない |
| 説明責任の原則 | 行政は、自らの行為の理由を国民に説明する義務を負う | ある政策を決定した場合、その決定の理由を国民に説明する必要がある |
信義誠実の原則
信義誠実の原則(信義則)とは、「行政は、誠実かつ公正に行動しなければならない」という原則で、要するに国民を裏切らないことを求めています。
例えば、行政が、ある事業に対して補助金を交付することを約束した場合、正当な理由なく、その約束を破ることはできません。
国または公共団体は国民の代表と呼べますから、国民を裏切らないは当然とも思えますが、工場の誘致における市町村の判断を認めつつも賠償請求が認められたケースもありますので、押さえておきましょう。
濫用禁止の原則(権限濫用の禁止)
濫用禁止の原則とは、「行政は、法律の付与した権限を、その目的の範囲を超えて行使してはならない」という原則です。
簡単に言うと、職権濫用はダメだということです。
例えば、警察官が、職務質問の権限を乱用して、無関係な人々を長時間にわたって拘束することは許されません。
知事の行った行政活動の内容を浴場業の開業を阻止を目的とした行為として、行政権の濫用が認められるケースもありました。
比例原則
比例原則とは、「行政は、目的達成に必要な範囲内で、最も制限の少ない手段を選択しなければならない」という原則です。
例えば、騒音問題を解決するために、工場の操業を完全に停止させるのではなく、防音壁を設置するなどの、より制限の少ない手段を選ぶ必要があります。
止めてもらう方も大事ですが、止められる方のことも考えなければなりません。
平等原則
平等原則とは、「行政は、合理的理由なく、人々を差別的に扱ってはならない」という原則です。
先ほどの比例原則と似たような原則ですが、例えば、同じ条件の2人に対して、一方には許可を与え、もう一方には許可を与えないという行為は、平等原則に違反します。
比例原則は必要最小限の範囲で制限をかけるものなので、必ずしも平等にはならないと考えるとわかりやすくなりまうs。
ただし、合理的理由があれば、一定の差別は許容されます。
例えば、身体障害者に対して、特別な配慮をすることは、平等原則に反しません。
説明責任の原則
行政法の様々な条文たちに説明や広報といった文言を見かけますが、国民の代表である以上、説明責任は免れません。
そんな説明責任の原則とは、「行政は、自らの行為の理由を国民に説明する義務を負う」という原則です。
例えば、行政が、ある政策を決定した場合、その決定の理由を国民に説明する必要があります。
聞いてないし。という場合も実は、色々な手段や方法によって説明がされている場合がほとんどです。
まとめ
行政法の一般原則は、行政の行動を律する「当たり前」のルールであり、私たちの権利と利益を守るために必要不可欠なものです。
この記事では、行政法の一般原則を、法律による行政の原理と一般原則の2つに分けて解説しました。
まず、「法律による行政の原理」では、行政は法律に従って活動しなければならないことを規定しています。
法律は国会のみが制定でき、行政は法律に違反してはならず、国民の権利を制限する場合は法律の根拠が必要です。
次に、「一般原則」は、法律に明文化されていないものの、行政が遵守すべき基本的なルールです。
信義誠実の原則、濫用禁止の原則、比例原則、平等原則、説明責任の原則とありましたが、普通に考えるとわかるようなことも、判例となるとポイントや争点によっては小難しいと感じるかもしれません。
まずは、それぞれの原則がどのような意味と持って、どのようなケースが当てはまるのかということから知っていくと判例の知識も定着しやすくなります。
これらの原則は、行政の恣意的な行動を防ぎ、国民の権利と利益を保護するために重要な役割を果たしていることがわかります。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!
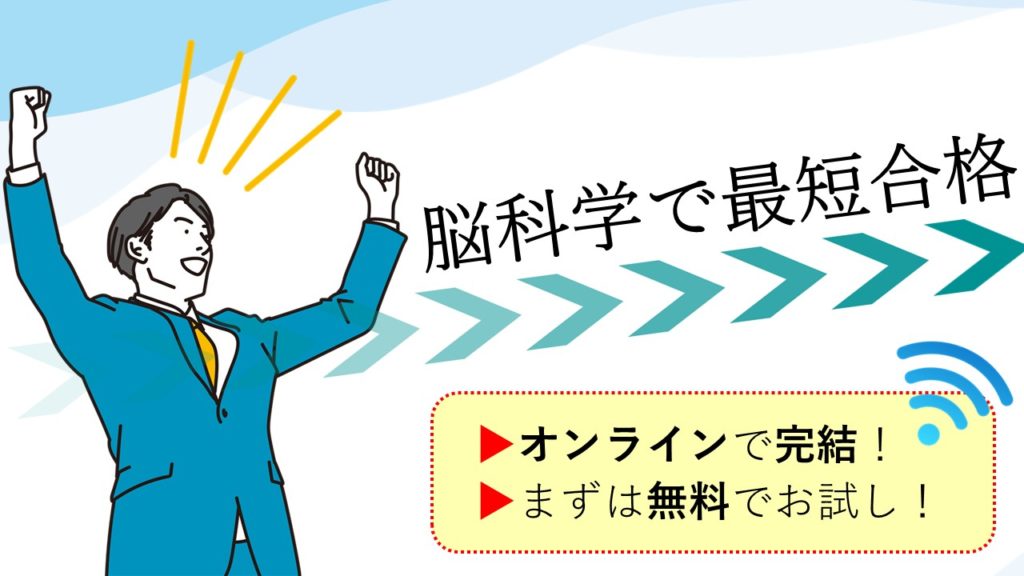
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。