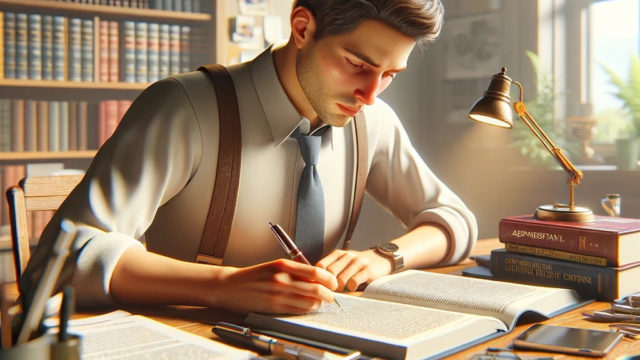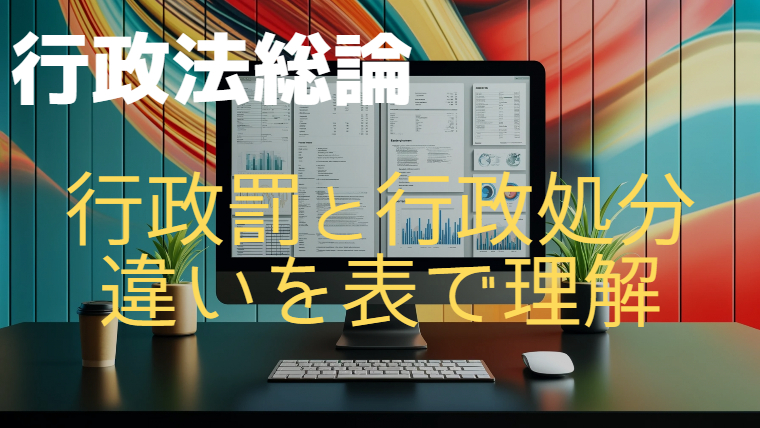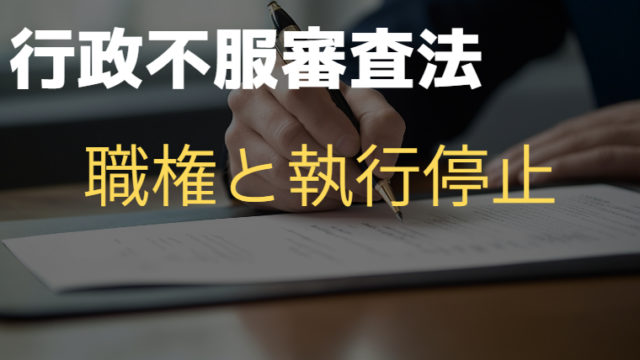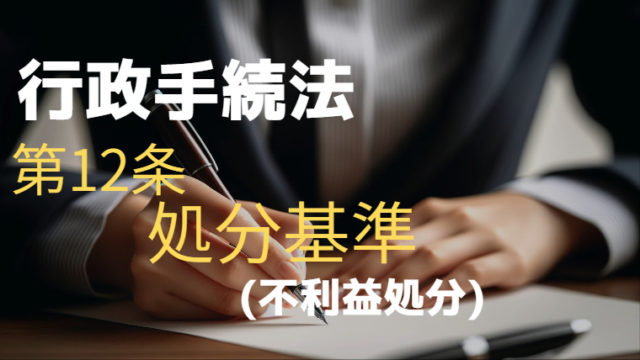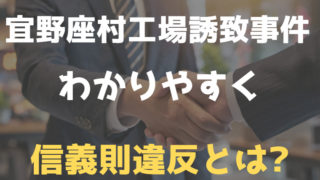行政罰と行政処分の違いについて、どちらも違反した人へのペナルティのようなイメージですが、一体何が違うのでしょうか?
行政罰と行政処分は、どちらも行政上の違反に対する対応ですが、その目的や性質、種類、法的拘束力などが異なります。
行政罰は違反行為に対する制裁を目的とし、行政処分は公益の保護や個人の権利利益の調整を目的とします。
- 行政罰と行政処分の違い:違反行為への「お仕置き」である行政罰と、社会秩序を守るための「調整」である行政処分。その目的や性質が大きく異なります
- 行政罰の種類と具体例:秩序罰(過料など)と行政刑罰(拘留、科料、罰金、没収など)について、身近な事例を交えて解説します。
- 行政処分の種類と具体例:許認可、命令、行政指導など、行政処分が持つさまざまな手段とその目的を解説します。
この記事では、行政罰と行政処分の違いをわかりやすく解説していきます。
それぞれの違いをひとつずつ理解していきましょう。
具体例や表を使ってポイントも交えながら、一緒に学んでいきましょう!
行政書士試験の準備にお悩みの方へ。複雑な試験範囲や不安を解消し、自信を持って合格を目指すなら、資格スクエアの行政書士講座がおすすめです。
柔軟な学習スケジュールや24時間対応のサポート体制が整っており、スマホやPCから気軽に学習できます。
経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。

行政罰と行政処分、根本的な違いは?
行政罰と行政処分は、どちらも行政上の違反に対する対応ですが、その目的や性質が大きく異なります。
まずは違いを表で見てみましょう。
| 区分 | 行政罰 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 目的 | 違反行為に対する制裁 | 公益の保護・増進、個人の権利利益の調整 |
| 性質 | 懲罰的 | 規律的・調整的 |
| 種類 | 秩序罰(過料など)、行政刑罰(拘留、科料、罰金、没収など) | 許認可、命令、行政指導など |
| 法的拘束力 | あり | あり(行政指導を除く) |
| 対象 | 義務違反者(個人・法人) | 不特定多数の者または特定の者 |
| 手続 | 刑事訴訟法の規定の一部準用 | 行政手続法の規定による |
| 救済 | 不服申立て、国家賠償請求 | 不服申立て、取消訴訟 |
行政罰:違反行為への「お仕置き」
行政罰は、例えるなら「お仕置き」のようなものです。
何か悪いことをしたとき、親や先生から叱られたり、罰を与えられたりした経験はありませんか?
行政罰もこれと同じで、違反行為に対して制裁を加えることで、再発防止を促すことを目的としています。
行政処分:社会秩序を守るための「調整」
一方、行政処分は、社会秩序を維持し、公益を守るための「調整」のようなものです。
交通ルールや建築基準など、社会生活を円滑に進めるためのルールを守らない人がいた場合、行政処分によってその状態を是正し、社会全体の利益を守ります。
行政罰の種類と具体例
行政罰には、大きく分けて「秩序罰」と「行政刑罰」の2種類があります。
秩序罰:行政秩序を守るための罰(義務違反)
秩序罰は、行政上の秩序を維持するために科される罰です。
代表的なものとして「過料」があります。
※なお行政刑罰で課されるのは科料です。
過料は、比較的軽い違反行為に対して科される金銭的な罰です。
例えば、ごみのポイ捨て、駐車違反などに対して、過料が科されることがあります。
行政刑罰:刑事罰に近い罰
行政刑罰は、刑事罰に近い性質を持つ罰と覚えておきましょう。
自由を奪ったり、財産を没収したりするなど、より重い制裁が科されます。
また、違反した人だけではなく、雇い主、事業主に対するなど両方に罰を与える規定を設けることもできるので押さえておきましょう。
行政刑罰には、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、○刑があり、刑法が適用され刑事裁判によって科されます。(刑事訴訟法)
「科料」となりますので、「過料」とは違うので注意しましょう。
行政処分:公益を守るためのさまざまな手段
行政処分は、公益を守るために、行政機関が国民に対してさまざまな手段で行う行為です。
許認可:特定の行為を許可または不許可する
許認可とは、特定の行為を許可または不許可する行政処分です。
例えば、飲食店の営業許可、運転免許の交付などが該当します。
許認可を受けるためには、法律で定められた基準を満たす必要があります。
例えば、飲食店の場合は、衛生管理が適切に行われていることなどが求められます。
命令:一定の行為を命じる
命令とは、国民や企業に対して、一定の行為をするように命じる行政処分です。
例えば、違法建築物に対して、是正命令を出す、騒音規制法に違反している工場に対して、操業停止命令を出すなどが該当します。
命令には、法的拘束力があり、従わない場合は罰則が科せられることもあります。
行政指導:任意の協力を求める
行政指導とは、国民や企業に対して、ある行為をするように、またはある行為をしないように指導する行政処分です。
例えば、節電の呼びかけ、食品の安全に関する注意喚起などが該当します。
行政指導には、法的拘束力はありません。
しかし、行政機関からの指導は、国民や企業に対して大きな影響力を持つことがあります。
ただ、行政の立場から教えるということであることを覚えておきましょう。
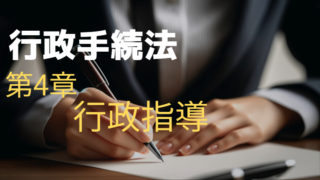
行政処分と行政指導は、どちらも行政機関が行う行為ですが、法的拘束力の有無が大きな違いです。
行政処分には法的拘束力がありますが、行政指導にはありません。
つまり、行政指導に従わなくても、罰則を受けることはありません。
しかし、行政指導を無視し続けると、最終的には行政処分が行われる可能性もあります。
まとめ
行政罰と行政処分は、どちらも行政上の違反に対する対応ですが、その目的や性質、種類、法的拘束力などが異なります。
行政罰は、違反行為そのものに対する「お仕置き」として科される制裁です。目的は、違反者個人への懲罰と再発防止にあります。
例えば、駐車違反で切符を切られる、食品衛生法違反で営業停止処分を受ける、税金を滞納して延滞金を払うといったものが行政罰に当たります。
一方、行政処分は、違反状態を是正し、社会全体の利益を守るための「調整」です。公益を守るために、行政機関がさまざまな手段で行います。
例えば、飲食店の営業許可や建築確認申請の許可といった許認可、違法建築物への是正命令や騒音規制法違反の工場への操業停止命令といった命令、さらには節電の呼びかけや食品の安全に関する注意喚起といった行政指導も行政処分に含まれます。
行政罰は違反者個人に焦点を当て、行政処分は社会全体の利益に焦点を当てているという違いがあります。
また、行政罰には法的拘束力があり、違反すると罰則が科せられますが、行政指導には法的拘束力はありません。
行政罰と行政処分の違いを正確に理解することが求められます。
それぞれの目的、性質、種類、法的拘束力などをしっかりと把握しておきましょう。